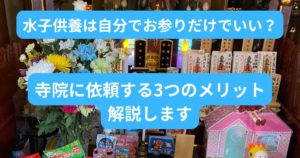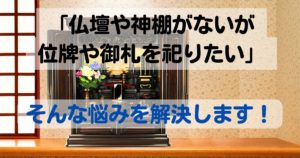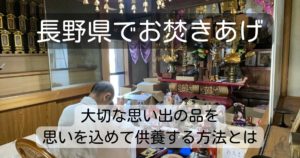みなさんは「数え年」という概念をご存知でしょうか。
この数え年は普段使用している「満年齢」とは数え方も、考え方も異なります。
一見すると「ややこしい」側面もありますが、一度理解をすればそれほど難しいことはありません。
また数え年の由来を知ると、より身近な存在に思えるようになることとおもいます。
この記事を読むことで
◯正しい「数え年」の数え方がわかり、厄年や七五三などの際に計算を間違えることが無くなる
◯「数え年」の意味や由来がわかり、未だに用いられている理由がわかる。
こういったメリットがあります。
現在、私はお坊さんとしてご供養や御祈祷を中心にお仕事をさせて頂いており、「数え年」にふれる機会が多いです。そんな私が仏教の知識をベースによく頂く質問や疑問などを交えて語っていきます。
それではいきましょう!
数え年とは?
「数え年」とは本来の誕生日に迎える年齢ではなく、お正月を迎えるごとに年を重ねるという数え方です。
生まれた時点の年齢を「1歳」とし、以後お正月が来るごとに「1歳」を加えます。
それに対して、現在使われている「満年齢」は、生まれた時点の年齢を「0歳」とし、以後誕生日に「1歳」を加えます。
ようするに、満年齢よりも数え年の方が年齢が上になるわけですね。
数え年はどうやって数えるの?
誕生日前 ⇒ 満年齢+2歳
誕生日後 ⇒ 満年齢+1歳
これが一番簡単な数え方です。
これさえ覚えておけばバッチリですね。
不安な時は確認の意味も込めて、お寺や神社に尋ねてみて下さい。
一般の人よりも「数え年」にふれる機会が多いので、優しく教えていただけると思いますよ。
数え年に関するよくある疑問をまとめました
さて数え年の意味や数え方はわかりました。
それではもう少し深掘りしてみましょう。
私がよくお施主さんや相談者さまからいただく「よくある質問」をまとめてみましたのでみていきましょう。
疑問1:数え年はどんな時につかうの?
まずよくある質問です。
どんな時にこの「数え年」を使うのでしょうか。主なものを見ていきましょう。
①七五三

七五三(しちごさん)は、昔から行われていた
3歳の「髪置きの儀」
5歳の「袴着(はかまぎ)の儀」
7歳の「帯解(おびとき)の儀」
に由来するもので、現在も3歳・5歳・7歳にお祝いをします。
この年齢は、満年齢ではなく「数え年」で行うのが正式とされていました。
ただ現在は「満年齢でおこなってもよい」とする考えが主流となっています。
地域差や両親と祖父母の世代による意見の相違もありますので、相談しながら取り決めるのが無難ですかね。
当寺でも「七五三祈祷」を行っております。
子供の守り神である「鬼子母神さま」の御宝前にて「成長完全、発育増進」をご家族とともに祈願します。
そしてご先祖さまにも我が子の晴れ姿を見ていただくようにご供養も一緒に行うようにしております。
お寺で行う場合は「数え年」にておこなうようにおすすめしています。
ただ、お施主さんが満年齢で申し込んだ場合はその考えを尊重するようにしております。
②歳祝い(長寿祝い)

61歳の「還暦(かんれき)」
70歳の「古希(こき)」
77歳の「喜寿(きじゅ)」
80歳の「卒寿(そつじゅ)」
88歳の「米寿(べいじゅ)」
などの年祝い(長寿祝い)は数え年で数えるのが一般的です。
ただ「七五三」同様、最近では満年齢でお祝いする方も多くなってきました。
長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられていて由来があります。
ここでは詳しくは解説しませんが、感謝の気持ちといつまでも長生きしてほしいことを願ってお祝いしてあげたいものです。
ちなみに、還暦は「お祝いの年」でもあり「厄年」とする場合が多いです。
③厄年

厄年は数え年を使います。
満年齢が用いられることは上記2種に比べると少ないです。
満年齢で考えると「いつの間にか厄年が終わっていた!」ということになります。
当寺で「厄払い」を満年齢で申し込まれた方には、数え年で考えるように伝えます。
さらに、そういった方には
「厄年は終わっていますが仏さまに何事もなく厄年を過ごせたことを感謝しましょう」
と伝え、ご一緒にお礼参りとご希望があれば今年一年の「厄除開運」をご祈願するようにしております。
こうすることで「厄年すぎちゃったけど何もなかったし、まあいいか!」と安直に考えるのでなく何事もなかったことへの感謝を伝えることができ、よりご加護をいただけると、私は考えております。
④享年(行年)

亡くなった年を示す享年(きょうねん)や行年(ぎょうねん)にも殆ど数え年を用います。
ただ仏式、神式以外では満年齢を用いる所もあります
⑤年回忌(一周忌を除く)

仏式で用いられる三回忌、七回忌、十三回忌、、、などの年回忌では数え年に準じて数えます。これは満年齢に準じた数え方は絶対にしません。
ただ、「一周忌」のみはこの数え方ではなく、「1年経過した年」に行います。
これは「亡くなってから一年が過ぎましたよ」ということですので、一周忌のみ「周」の字が使用されているわけですね。
疑問2: 数え年はなぜ生まれた日を「1歳」と数えるのか?
これもよくいただく質問ですが、なぜ数え年では「生まれた日を1歳と数える」習慣があるのでしょうか。
それは数える起点が「お母さんのおなかの中にいのちが宿った時」にあるからです。
この「いのちの大切さ」を重要視した考えは「仏教」の教え、考え方が起源とされています。
ですのでお寺では今でも数え年をより多く用い、重要視することが多いのですね。
日本では数え年の考え方は戦後まで主流でした。
しかし戦後に年齢に関する法律が施行され、満年齢を用いることが義務化されました。
余談ですが、現在も数え年を主に用いている国は『韓国』だけ、とのことです。
疑問3: なぜ「お正月に年を取る」と考えるのか?
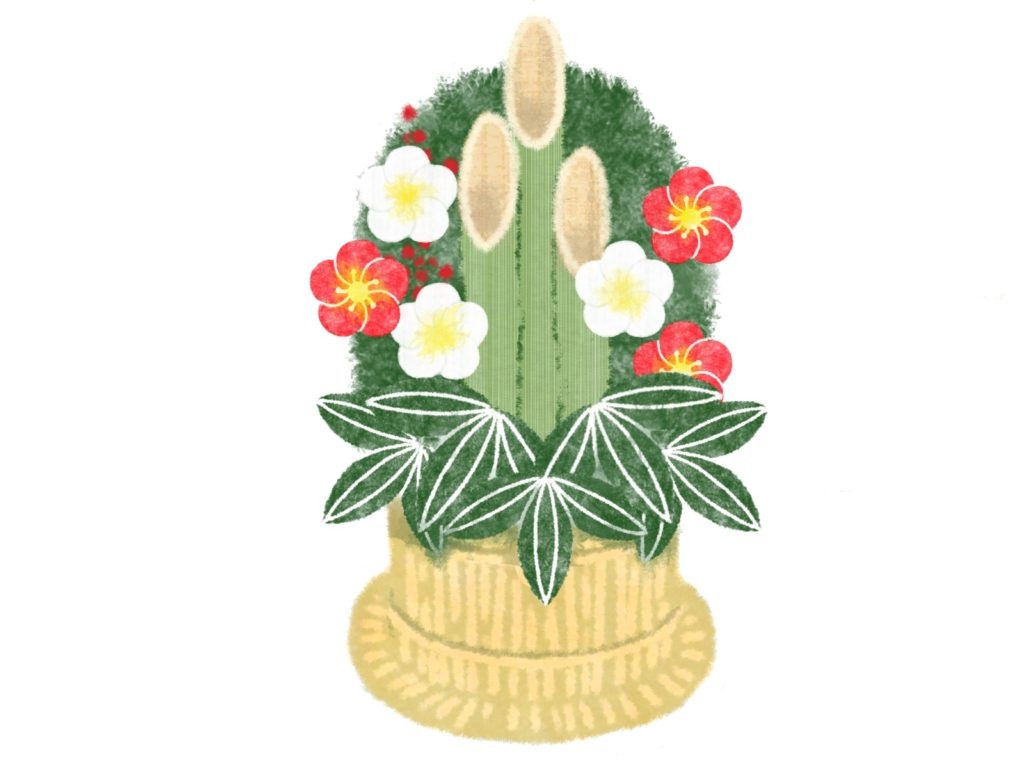
数え年の考え方では、お正月を迎えるとみなさんいっせいに年をとります。
数え年の考え方でもっとも難しいと思われる「この理由」について詳しく解説しますね。
それは日本で昔から大切にされてきた「歳神さま」との関係があります。
昔から日本ではお正月は「歳神さま」をお迎えする大切な日として非常に特別視してきました。
お正月を迎える年末に大掃除を行い、門松・しめ縄を飾り、鏡餅を用意します。
これらはもともとこの「歳神さま」を自宅にお迎えするための準備であったといわれています。
そしてこの「歳神様」からいただけるものが「お年玉」です。
「年」は「年神様」、「玉」は「たましい、霊力」のことを示すといわれ、これをいただくことにより『一年分の生きる力をいただける』という言い伝えがあります。
よって
お正月が来る = 歳神様が来る = お年玉をもらう = 一年分の力を得る = 年を取る
と考えるようになりました。
この考え方から「正月が来ると年を取る」と考えるようになったようですね。
お年玉にこんな由来があったとは、驚きですね。
「数え年」の考え方に思いを巡らそう

今回は数え年について詳しく見てきました。
普段はあまりふれる機会が少ない「数え年」ですが、こうして意味や由来を見てみると、あらためていのちの大切さや昔の人の思いというものをひしひしと感じます。
これから自分の厄年、子どものお祝い、親の歳祝いなどで「数え年」にふれる機会もあることでしょう。
その際は、「数え年」にある言い伝えや意味を思い出して、あなたの周りの大切な人やご先祖さまにに思いを巡らせてみて下さい。
それでは今回は以上です。